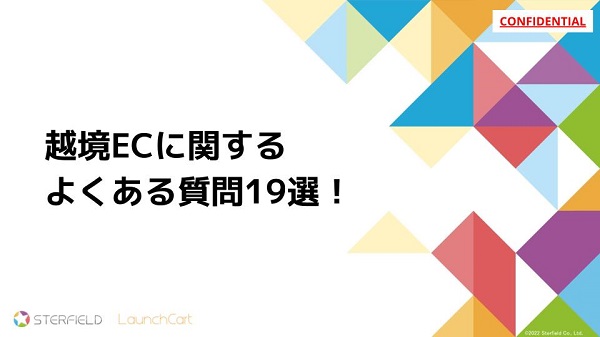【ゲストスピーカー】
成島 祐介さん
株式会社成島 代表取締役
雛人形と五月人形の「人形屋ホンポ本店」
【チャンネルMC】
柳田 敏正さん
株式会社柳田織物 代表取締役
ワイシャツ専門店「ozie(オジエ)」
この記事の目次
異文化に日本の伝統工芸品で参入して気づいたこと・得られたこと
人口減少を見据えて狙う海外市場
柳田さん:株式会社成島の人形屋ホンポを運営する成島さんは、節句人形を扱っていますが少子高齢化で業界的に伸びているとはいえない市場です。人形屋ホンポに限らず、人口の減少により誰しもが日本だけで事業を行っていくのが厳しいと感じている中で、越境ECにチャレンジしている成島さんに教えを請えればと思っています。そもそもどういうきっかけで越境ECを始められたのでしょうか。
成島さん:雛人形や五月人形のような伝統工芸品を主にECで約15年販売しています。子供が減っていたり、核家族化が進んでいたりといった中で、日本では節句人形を飾る意義や意味が伝わりづらい状況にあります。それはどの国でも一緒なのかなと思ったことから世界に目を向け始めました。
そして、国によって時代がそれぞれ違うので、日本が人形を大切にした時代と同じくらいの時代を過ごしているエリアがあるのではないか。もしくは、我々が培ってきた文化がハマるエリアがあるのではないかと思ったのです。
柳田さん:日本では文化が変わってきているものの、世界に目を向ければニッチではあるが目を向けてくれる方がいるのではないかと考えられたのですね。では、実際に越境ECをやられる中でどういったエリアに焦点を当てているのでしょうか。
成島さん:日本人と同じ髪色であるアジアを中心に見ています。例えば中国やベトナム、インドネシア、フィリピンなどですね。10年ほど前に、最初は上海に行きました。当時はビルがどんどん新しく建ち並び、言葉では言い表せない活気を感じたことを覚えています。他のアジアの国も一度訪れてから3年後に再訪すると、バイク社会から車社会になるなど、急速な変化が起きているのです。一方で、非常に発展しているように見えて、現地の方とコミュニケーションを取ってみると、日本では当たり前のものがその国にはないことが多々あります。
人形屋ホンポとしては、まず人形を現地に持っていきましたが、そのままでは全く相手にされませんでした。次にローカライズを考えるものの、そのやり方がわからないため勝手に現地の方の像を描いてやってみます。しかし、イメージでしかないので、結局ニーズに合いませんでした。
現地での試行錯誤が案件へとつながる
成島さん:試行錯誤を5年、10年と続けると、現地の方から良いフォードバックを頂けたり、人形に関わらず相談事を頂けたりするようになります。そういったニーズは、仲良くならないと教えてもらえないですし、わからないのです。
柳田さん:越境ECといっても日本からは出ずに情報収集して海外に販売しようする方もいますが、現地に長くいたからこそ見えてくることがあるんですね。実際に提供して喜ばれたのはどういった商品なのでしょうか?
成島さん:例えば中国にはダイエット系の食品がほとんどありません。糖質を抑えた食品やノンアルコールのビールなど、当たり前にありそうな気がするものが意外とないのです。
物に限らず、情報を提供することもあります。中国にはコインパーキングみたいなものがありません。それぞれのお店が駐車場を所有しているため、繁盛しているお店の駐車場は満車なのに隣のお店のはガラガラということも珍しくないのです。そこで、日本ではコインパーキングというものがあることを教えるのです。このような形で物や情報の交換を繰り返すうちに、壁の中に入れてもらえ、家族のように接してくれるようになります。
柳田さん:日本的な家族というよりはファミリーという言葉がしっくり来そうですね。逆に、中国の方から教えてもらってよかったことはありますか?
成島さん:向こうのトイレでは、鏡がディスプレイになっていて広告が掲載できるようになっています。例えば、そこで化粧品を選んでQRコードで決済することが可能です。また、居住区のエレベーターに広告が掲載できるようになっており、その分共益費が下げられる仕組みになっています。
柳田さん:私も中国で販売しているため、成島さんほどではないですが中国に行きますが、日本人とは根本の考え方が違いますよね。日本ではインフラが既に整っているがゆえできないこともあると思いますが、何かを実現するための強い力を中国では感じます。
新しい試みを実現するための社内コンセンサス
柳田さん:そのご経験から、現地の方々とお近づきになったということですが、海外販売は現在どういった状況になっているのでしょうか。
成島さん:海外で物を売ろうと考えると、我々のような中小企業には大変なことです。新しいことをするには、日々の業務があるためリソースが限られています。社内では「また社長が何か言い出した」「そのうち飽きるだろう」といった空気になり、コンセンサスを取りづらいです。
柳田さん:メインの事業が人形の販売である中、全く違う商品を販売するとなるとコンセンサスを取りづらそうですね。
成島さん:はい、ほぼコンセンサスは取れないです(笑)昔は社員の声を気にせず、関係なくやっていましたが、無理を通していたことを反省してからうまくいくようになりました。
柳田さん:物が実際に動くことになれば、社内の協力が必要です。現在は順調に運用できているのでしょうか。
成島さん:大体3年前からチームを組んで運用しています。在宅ワーカー10名程度で構成され、そのうち半分は副業で参加してもらっています。副業として参画いただいていても、仕事を楽しんでもらえると弊社の業務のウェイトが高くなり、社員になることもあるんです。
柳田さん:いろんな商品を中国で販売されていると思いますが、売上は人形の割合が多いのでしょうか?
成島さん:人形のほうが売上シェアは断然多いです。商品の製造や管理など海外の販売も始まっているのですが、中国現地でものづくりをしている方から製造の工程でアドバイスを頂くこともあり、国内販売にも活きていると感じます。
中国ビジネス市場開拓秘話!越境ECの新たな可能性
できる仕事を積み上げて信用を獲得する
柳田さん:人形という業界にいらして、活路を求めて足繁く海外に通った結果人脈が広がっていきました。いよいよ挑戦できることが増えてきた印象ですが、今後どういったことに取り組んでいくのか伺いたいです。
成島さん:今は滝のように仕事の依頼が押し寄せてきています。その中で依頼を選ばなければいけない状態です。最初はできるかもしれないくらいの気持ちで引き受けようかと思っていましたが、引き受けてできないと信用を失ってしまいます。なので、数ある依頼の中からしっかりとできる案件を選ぶようにしています。
依頼が来るものは結局、今までその国にはないものです。何故ないのか考えると、ないなりの理由があります。そのため、安易に依頼を受けずに数ある案件から絞っていくと原石のような案件が残るのです。
柳田さん:具体的に最近何か面白いお話はありましたか。
成島さん:少し前に爆買いがあったかと思います。日本国内の店頭では少し落ち着いたように見えますが、実は中国国内では爆買いは続いています。ただ、課税の基準などが厳しくなったことで店舗ではなく、通販や中国国内で購入されているのです。中国国内で売れているのは中国で生産されているものではなく、日本から入った日本の商品です。その入り方によって関税や課税のかかり方が異なります。中国政府としては海外で買い物されるよりも中国国内の消費が進むほうが税金を多く取れるため、そういった流れに乗れている事業者がよく伸びている印象です。
求められている商品自体は爆買いが行われていた頃と大きく変化はありません。例えばお米です。深センのスーパーに行くと70~80種類の日本産のお米がキロ1,200~1,500円くらいで売れています。ただ、食べてみるとそこまで美味しいわけではないのです。何らかの理由で非常に高い値段になっているのではと思います。
日本の中小企業を世界へ、ハードルを下げて適正価格で販売を
成島さん:私は高校・大学と茨城県にいましたが、全国に物を売るということは思いもつかなかったです。全国に売るのは大きな企業がすることで、中小企業は関東全域に売ることも考えられない時代でした。それが通販によって変わりました。今、日本には人口減少による閉塞感があります。通販の仕組みが日本全国に広がったように、世界に広げる構想を今のチームでやっています。
柳田さん:地方のお店がECによって販路を広げ、全国に売れるようになっているのは紛れもない事実です。人口が減少する中、日本だけで商売をしていては、と誰もが不安に感じていることだと思いますが、実際にやるとなると中小企業においてはハードルが高いことでしょう。
成島さん:そういった挑戦を中小企業でもできる座組を整える準備に取り組んでいます。中国では日本のお米が5倍や6倍の価格になっていますが、日本に通販が広がる前は地方の物の価格が非常に高かったのと同じことです。
日本国内はAmazonや楽天市場があることで、同じような商品は激戦です。しかし、海外に持っていくと、現地の方にとっては全く見たこともない商品に変わります。だからプライシングやニーズが変わるのです。以前の失敗では我々が売りたいものを海外に持っていっていました。今では、現地の方はニーズを頂けるので、そのニーズにセンスで商品を選んでいます。そういった商品を「なにこれ!」「知らなかった!」と感じていただき、適正価格で販売できることが中小企業として嬉しいこといえるでしょう。
柳田さん:メーカー直販によって中間コストを抑え適正価格で販売するD2Cがアメリカや日本で盛んになる中で、中国で販売価格が高くなるのは輸出しているからもありますが、間に人がたくさんはいっているかということもあるでしょう。そこをスッキリしてマッチングできるようにすることで、適正価格で商品をお届けできる感覚を広げていきたいということですね。
成島さん:いわゆる大企業を除き、1人会社を含めると99.97%が中小企業になります。そういった企業がちょっと元気になると、全体に与えるインパクトは非常に大きいです。自分の経験から選んだ商品を見せることで、驚き、購入し、リピートしてくれるのは商売の原風景に近いのではと思います。
柳田さん:日本から持ち出すとなると、海外とは人件費が違う部分もあります。成島さんを見ると、日本から安価な商品を海外に売っていくのとは違う気がします。中国のように格差が広い国では、裕福な方にアプローチできれば良い気がするのですが、ターゲットについてはどうお考えでしょうか。
成島さん:ターゲットの層はコチラで選ばないようにしています。現地の方からこういうのが欲しいと相談を受けたときに、できそうだからという理由でやることが大半です。
協調で目指す海外市場の成功
成島さん:私は電動キックボードが好きで何個か輸入しているのですが、メーカーがクラウドファンディングをしている様子を見て、私が考えたほうがうまくできそうだと思ったんです。
日本で売ろうとすると道路交通法などの諸問題が挙げられますが、アジアの人から「あなたが考えて他の国でクラウドファンディングすればいいじゃない」と言われて寝耳に水でした。日本人が製造から販売まで全部やるのではなくて、商流の間に入ってアシストすることで価値を出せる瞬間があることに気づいたのです。
柳田さん:1人では難しいけど皆で手を組んでやったらできることが多そうですね。日本から海外のクラウドファンディングに出るアイディアはなかったです。
成島さん:欲しい人がいて、良いものを作り、それを応援したい人がいれば成立するので、たしかにどの国で実施するかはあんまり関係ないと思ったんですよね。海外の方からアイディアを頂くと、閉塞感が開けて違う見え方ができるようになります。
柳田さん:自分たちの常識を外さないと駄目ですね。アジアの中で中国がわかりやすいですが、とても合理的な考え方をする方々だと思っています。自分が便利に、自分のためにという考え方です。日本の場合は、足を一歩前に踏み出せない方が多い印象があります。外に出ていくなら常識を外していかないとついていけません。逆に言えば私たちも伸び伸びできていない部分があるんだろうなとお話を聞いていて思いました。
成島さん:20代中頃くらいのハーバード大学で勉強して中国に戻ってきた海亀族と呼ばれる若者たちが「明日から寝ないで3年後に上場だ!」と給料ゼロで株を分け合っている姿を目にしました。そういうことが目の前で起きていると我々のマインドではついていくのが難しいと感じます。しかし、戦うのではなく、協調できれば面白いと思うんです。
彼らは若すぎて挫折することもあるかもしれない。そういうときにアシストできることがあって、うまくいければ我々の価値を発揮できると思います。
柳田さん:お互いが違う土地でビジネスをするのは大変だから、手を組んで、お互い協力しあって、皆が幸せになればいいよねという考え方ですね。
おわりに: 海外販売で大事なのは現地の方を知ること
日本国内での商売は、生まれ育った国の使い慣れた言葉で、文化や商習慣など言語化せずとも肌で感じながらできることは多いはずです。しかし、海外に展開する場合、日本から販売する優位性以上に現地の方をよく知ることが大切ではないかとお話を聞いて感じました。
成島さんは中国をはじめアジアに10年以上渡航を繰り返し、現地の方々と密なコミュニケーションを交わしています。システムだけでなく、物流・配送面も徐々に整備され、海外販売のハードルは下がりつつありますが、商品を購入する現地の方を知ることは容易なことではないかと思います。海外進出を検討中の方は、実を結ぶまで時間がかかることを視野に入れて取り組まれると良いのではないでしょうか。
EC市場の真の発展に貢献をという想いで、「ECの未来」を運営しているサヴァリ株式会社は楽天市場・Amazonなどネットショップ運営代行をはじめ、モール通販を中心にECサポート・ECコンサルティングを行っています。EC運営に不安を抱えている事業者様は問い合わせてみてはいかがでしょうか。
■サヴァリ株式会社へのお問い合わせはこちら
https://savari.jp/contact/
合わせて読みたい