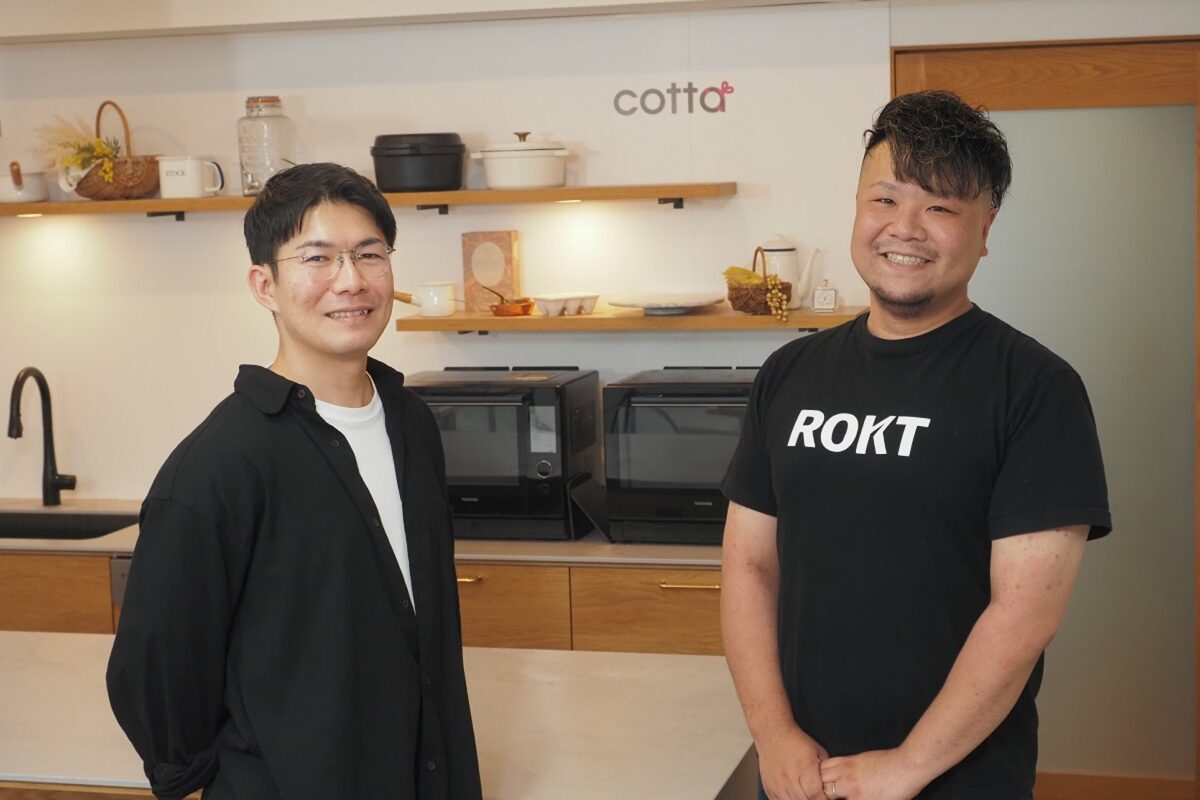
Rokt合同会社 ビジネス開発 久保 信輝さん(写真:右)
製菓・製パン用の材料などを取り扱うECサイト「cotta」は、業界内で日本最大級のECメディアプラットフォームとして展開しています。EC事業とは別に、月間2,000万PVというアクセス数の多さを活かして、広告事業を進めてきた中で、従来の広告手法では「関連性の薄い広告が表示される」「ブランドイメージが損なわれる」といったユーザー体験の課題がありました。
その課題を乗り越える新たな施策として導入したのが、「Rokt Thanks」。従来活用しきれていなかったサンクスページにおいて、ユーザー体験を損なうことなく、関連性の高いオファーを提示し、新たな収益源の確立と成長投資の好循環を実現しています。
Rokt Thanks導入の背景、導入後の状況やそれを踏まえた今後の展開について、株式会社cottaの取締役を務める黒須則彦さんに伺いました。
この記事の目次
多様な顧客ニーズに応じたサービスを複数展開することで市場変化に対応
――はじめに、cottaさんがどのような事業を展開されているか、お教えください。
黒須さん:弊社は、製菓・製パン用の材料などを取り扱うECサイト「cotta」を運営しており、業界では日本最大級のECメディアプラットフォームです。cottaはもともとBtoB向けのECサイトとしてスタートしましたが、市場環境の変化やお客様のニーズの高まりを受け、BtoC向けにも展開するようになりました。
現在、「cotta」というプラットフォームを軸に、一般のお客様向け、法人向けに加え、健康志向の商品を扱う「cotta tomorrow」など、ニーズに応じた多角的なサービスを展開しています。こうした柔軟な展開によって、お客様との接点を増やし、サイトへの訪問頻度の向上にもつなげていきたいと考えています。
PVを活かした広告収益化に挑戦!立ちはだかったブランド毀損リスク
――広告事業を始めたきっかけは何でしたか?また、広告事業を展開するなかで、どのような点を課題に感じられていましたか?
黒須さん:cottaの月間2,000万にのぼるアクセス数は非常に大きな資源であり、この資源を有効活用して広告化できないかと、以前から模索していました。
最初に取り組んだのは、ネットワーク広告や動的ディスプレイ広告です。一定の収益効果はあったものの、広告内容に課題がありました。たとえば、関連性の薄い広告が表示されたり、排除しているはずの競合の広告が出てしまったり、一時期は好ましくない印象のサイトへ遷移するような広告が表示されたことも。社内からも慎重な声が多く、本格展開には踏み切れずにいました。
Rokt Thanks導入の背景は?未開拓領域のサンクスページを活用
――広告に対して慎重な姿勢があった中で、Roktの導入に至った背景には、どのような経緯があったのでしょうか?

黒須さん:Roktのことを知ったのは知人からの紹介がきっかけです。最初に「サンクスページを活用した広告」と聞いたときは、正直あまりピンときませんでした。
というのも、私たちもサンクスページではF2転換を目的としたクーポン表示など、CRM的な使い方はしていましたが、「すぐに閉じられるページ」という認識が強く、重要なページとして捉えていなかったんです。
ただ、その後にふと思い出したのが、映画館のサイトでチケットを購入したときのサンクスページです。私は映画が趣味でよく行くのですが、そのとき見かけた広告は、ユーザーとしてあまり嫌な印象がなく、むしろ「クリックしてもいいかな」と思えた経験がありました。それを思い出して、「一度話を聞いてみよう」と思ったんです。
わずか2週間で導入、社内も納得したRoktの柔軟な運用設計
――導入を検討する中で、懸念点や社内での課題などはありましたか?
黒須さん:やはり最初は「関連性の薄い広告が出てしまうのでは」という懸念がありました。ただ、初回の打ち合わせでRoktから広告配信のロジックを丁寧に説明してもらい、実際の表示例も確認したことで、不安はすぐに解消されましたね。特に、競合の広告はもちろん、ネットワーク広告や動的ディスプレイ広告で制御が難しかった旅行やレンタカー関連のようなcottaのイメージと乖離がある広告や、センシティブな内容の広告を事前にブロックできる点は、大きな安心材料でした。
――実際の導入作業に関しては、どのような体制や工程で進められたのでしょうか?
黒須さん:弊社はインハウスのエンジニアがいて、初回ミーティングでRoktに提示してもらったスケジュールに対して厳しい反応をしなかったので、難しい話ではないのだと考えていました。
導入に必要な作業はタグを埋め込むだけで対応ができたのと、用意するデータもマスターデータの一部だったので、私の感覚としても、それほど大きな工数はかからないだろうと。実際、決定からわずか2週間と短期間で導入が完了しました。
――広告のデザイン面での対応や社内からの評価はいかがでしたか?
黒須さん:それも最初の打ち合わせのときに、Roktからデザイン面の柔軟性について説明してもらい、社内のデザイナーも問題ないという反応でした。除外したい広告主やカテゴリを細かく設定できる点や、バナーではなくテキストベースで、特別感のあるオファー的な見せ方ができる点も、良いと感じています。
それでも導入して1か月くらいは、「お客様から何か問い合わせが来るのでは」と心配していました。弊社はコールセンターも自社で運営していて、何かあれば私の耳に入るようになっているのですが、特段何もなかったので安心しましたね。以前は広告に対して難色を示していた社内のメンバーも、Rokt Thanksに関しては好意的な反応を見せています。
少ない工数で収益性アップ!再投資が生む、成長と収益の好循環
――Rokt Thanks導入後の広告収益はどのように変化しましたか?また、それをどのように捉えているかお聞かせください。

黒須さん:導入前にRoktから提示されたシミュレーション通りの範囲で、広告収益は安定して推移しています。導入初期の数か月で調整を重ねたことで、しっかり結果が出る状態になりました。ECで同じだけの利益を出すための労力を考えると、非常に効率の良い施策だと感じています。
また、ネットワーク広告や動的ディスプレイ広告は収益が落ちた際に、自分たちで最適化の調整をする必要がありますが、Roktではそうした対応は不要です。広告主やカテゴリの除外設定も事前に伝えておけば、導入後に手を加える必要がありません。
何よりも驚いたのは、サンクスページのみに表示しているRokt Thanksの広告収益が、サイト全体に掲出しているネットワーク広告や動的ディスプレイ広告と同等、あるいそれ以上だった点です。
おそらく、cottaのユーザー属性や行動パターンとの親和性が高いことも、好結果につながっているのかもしれないです。弊社のユーザーは、30代後半〜50代のお菓子・パン作りが好きな女性が中心で、サイト内を回遊しながら「何を作ろうかな」とレシピを探し、材料を確認し、レビューやレコメンドも参考にしながら購入に至るという、比較的複雑なカスタマージャーニーをたどる傾向があります。私たちも、そうしたお客様の“ワクワク”を後押しする設計を意識しており、パルス(突発)的な購買を促進しています。
EC統括責任者としての視点では、広告収益が増えたことで「自由に使える予算が増えた」という感覚がありますね。たとえば「前年より利益がこれだけ増えたから、この分は新たな施策に再投資できる」といった判断がしやすくなり、結果的に成長にもつながっています。
広告収益を原資に新たな施策へ投資し、その結果としてサイトのアクセスが増え、さらに広告収益も伸びていく。こうした好循環が生まれつつあると感じています。少ない工数でこの流れを構築できたことは、長期的に見ても非常に大きな意味があるのではないでしょうか。
オンラインとオフラインのデータを循環させ、広告展開に活用
――今後、広告事業をどのように展開していきたいと考えていますか?

黒須さん:今後は、オンラインとオフラインを行き来するような広告施策に取り組んでいきたいと考えています。その一環として、先日、メーカー様をお招きした展示会を開催しました。オフラインの場で得たお客様との会話や反応といった情報をオンラインでの広告展開に活用する。また、Rokt Thanksで得られたユーザーインサイトをもとに、メーカー様へのフィードバックを行ったりと、BtoBとBtoCの両面から価値創出を図る構想です。
cottaにとっては、メーカー様もお客様であり、店舗で商品を手にするエンドユーザーもお客様です。どちらの立場も理解できるからこそ、Roktとの協業で得られた知見を循環させながら、双方にメリットのある提案を続けていきたいと考えています。
▼Roktのソリューション・製品はこちら
https://www.rokt.jp/
あわせて読みたい
















